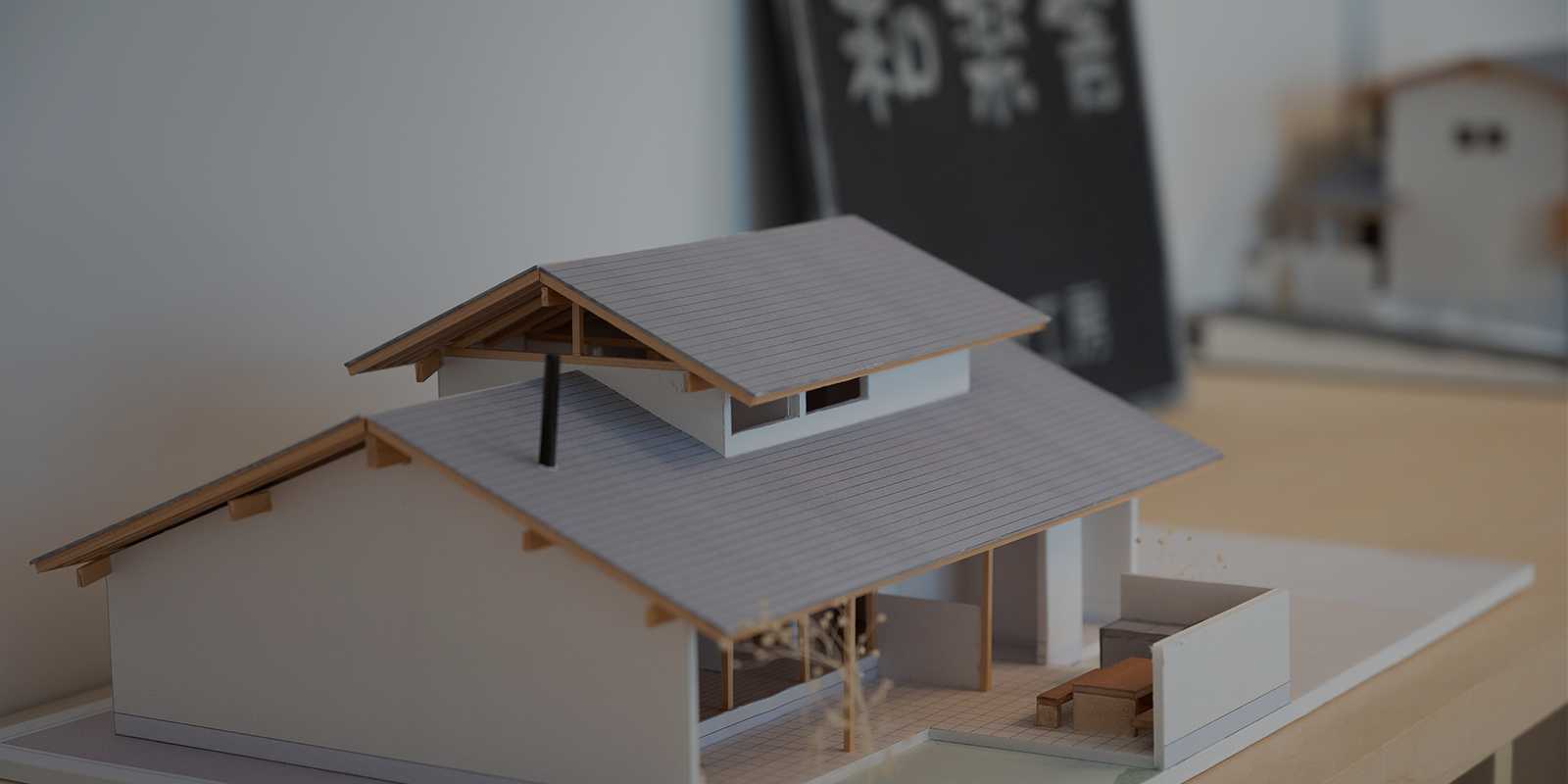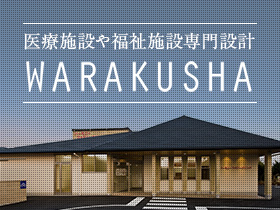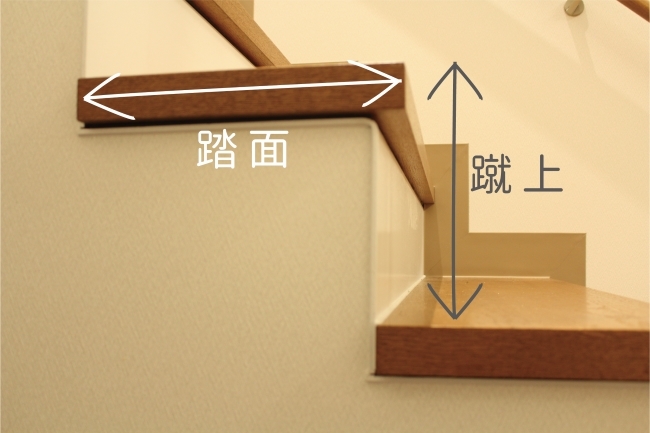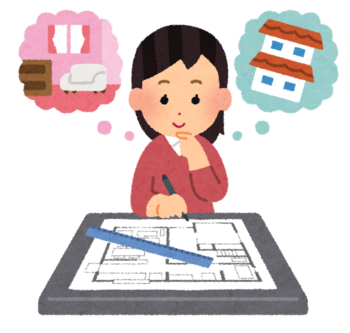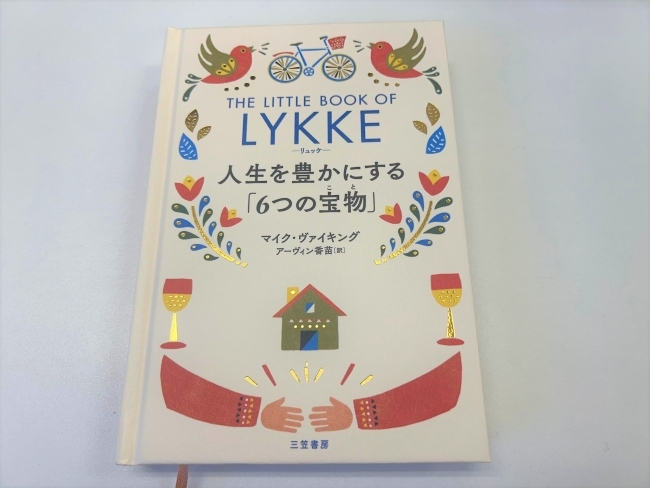ロシアによるウクライナ侵攻の被災者に対する、
建築家 坂 茂氏の支援が話題になっています。
難民としてウクライナの周辺国に避難した人々の避難所に、
「紙の間仕切システム」を設営したのです。
「紙の間仕切システム」とは、坂氏が生み出した簡易的個室のこと。
紙管を骨組みに、布をカーテンのように掛けて空間を仕切りします。
Paper Partition Systemの名称から、通称PPSと呼ばれるシステムです。

写真:日経XTECH
2011年の東日本大震災を皮切りに、
国内外の災害避難所にこのシステムが使用・重宝されてきました。
特に東日本大震災の際は大きく報道もされたので、
見覚えのある方も多いかもしれません。
今回の支援について坂氏は、
「テレビで難民の受け入れ施設が映ると、
人々が雑魚寝している状況だった。
プライバシー確保だけでなく
感染症対策の観点でもPPSの必要性を感じ、
すぐに支援しようと思った」
とコメントされています。
坂 茂氏は元々、
紙管を建築の構造材として使うことで知られる建築家です。
避難所においても安定した品質で
プライバシー保護機能を確実に遂行し、
しかも美しいシステムが提供されているのは
建築家として紙管と「仲良く」してきた
バックグラウンドあってこそですね。
ちなみに、ここ静岡県にも坂氏の設計した建築
「静岡県富士山世界遺産センター」
があり、先日行ってきました。
こちらでは、椅子の背面と座面が紙管で作られています。
シンプルで愛嬌あるデザイン。
座ってみると硬さと丸み、優しい質感が絶妙なバランスでした。
※建築について
「逆さ富士」の形をした展示棟は、
水盤に「富士山」の形になって映る圧倒的なデザイン。
展示棟内部は、
らせん状に登山するように登りながら
展示物を見ていく順路になっています。
そして…建物上部からは、本物の富士山が展望できます。
壁を覆うのは「富士ヒノキ」なるブランド木材で、
全部で6,973ピースの部材が
編み込んだように組まれています。
避難所の紙管と、景勝地の紙管。
心身に安心・安全を提供すること。
美しさに心動かすきっかけをつくること。
どちらも建築家の社会的な役割であり、
プロとしての姿勢を改めて学んだ出来事でした。
参考:
(スタッフ:里沙)
【works(浜松 磐田)】
【works(浜松 磐田)】
【top】